朝のNHKニュースを聞いていてびっくりしました。 愛知県産の米って、1等米が20.7%しかないのか!って。
ことしの新米の9月末時点の等級検査の結果は、最も評価が高い「1等米」の割合が岐阜で36.9%と去年の同じ時期を上回った一方、三重と愛知では去年を下回り、夏場の高温によって一部のコメに影響が出ているとみられます。
▽愛知県も20.7%で去年を1ポイント下回り、夏場の高温によって一部のコメに影響が出ているとみられます。
てか、1等米とか2等米って良く聞くけど、何が違うか説明できます?(僕はできなかった) そりゃ、1等米の方が高級(高価)だろうって?まあそうなんですけど、
お米の品質は『等級』で評価され、評価が高い順から1等米・2等米・3等米・規格外に分類されます。『等級』は、きれいな粒の割合や、虫に吸われて色がついたお米や異物の混入割合などによって格付けされますが、猛暑によって白い粒が多く発生した場合、平年よりもきれいな粒の割合が減少して、2等米以下の割合が高くなってしまいます。
じゃあ、1等米と2等米ってどっちが美味しいお米だと思います? そりゃ・・・
答え、味の差はありません。 えっ? もう少し読んでな。
もちろん、虫に食われてたり、異物混入があったら違うかもしれません。が、その辺りは現在の農業技術を使えば防ぐことが可能ですから、この点はあまり気にしなくていいでしょう。気になるのはこの文言です。
「猛暑によって白い粒が多く発生した場合、平年よりもきれいな粒の割合が減少して、2等米以下の割合が高くなってしまいます。」
あー、これ米つくってるとよくわかります。でも猛暑が常態化してる中、米粒が白濁化するのははっきり言って自然現象です。自然現象を理由に等級が決まったり、なにより見た目だけで等級が下がる(当然価格も下がる)ってのはちょっと納得がいかないなあ。
白濁化の理由は、お米の中には栄養分であるデンプンが詰まっていますが、このデンプンが貯まってくる時期に気温が高すぎると、詰まりが悪くなってしまい、それによってお米の中で光が乱反射することで白く濁って見えるのです。
・・・お米の品質は、等級によって分類されることはお伝えしましたが、これは見た目の評価であり、味の評価ではありません。等級が低くても味は変わりませんが、今年のように白い粒が多い場合は、通常の水分量で炊飯すると、割れた粒が多くなり、水を吸いすぎて柔らかくなりすぎることで、見た目や食感を損なう恐れがあります。
県では、実際に1等米・2等米・3等米・規格外で等級別に食味試験を行いました(炊飯時の加水量は同じ)。
その結果、1等米と2等米の間に食味の差はありませんでした。一方で、3等米や規格外では、水分のベチャつきが感じられ、食味は1等米に比べて劣る結果となりました。同上
「記録的な猛暑は、収量そのものを激減させるだけでなく、米の品質を根底から破壊しました。高温障害による『白未熟粒(お米が白く濁ってしまう現象)』が多発し、米の等級を決定する『一等米比率』は著しく低下しました。現場では、これまで1反あたり11〜12俵(約660〜720kg)獲れていた田んぼが、7〜8俵(約420〜480kg)しか獲れない、という声が私の周りでも数多く上がっていました」
農家ができる対策は「田んぼの水を絶やさず、常に新しい冷たい水を流し続ける」といった対症療法。自然の猛威の前では、個々の努力は限界に達していたのだ。
等級試験関連のニュースで、コメ袋に刃物を突き刺して米粒を抜きだす、下の写真はよく見ますけど、実質この視認だけで等級が決まるってことですな。僕の記憶だと、このあとエライサンが試食する画像が付随することが多い気がしますけど、味は関係ないということは、あれって試験と関係ない、ただのパフォーマンスだったんだな。

見た目はともかく1等米と2等米で食味は変わらないなら、そんな区分は無くせばいいと思いません?米の状態で水の量変えて炊飯するのは、まあ消費者の好みでやればいいがな。
特に今年はコメ不足(流通遅れ?)だったんだから、見た目だけの等級をつけるためだけの手仕事、なんていう前時代的なステップはやめたらいいのに。どうしてもやるなら、食味計で旨さ等級をつけるなら、まだしも、見た目、ねえ。
まあそれを含め、僕らは主食として日常的にコメを食べているのに、そしてその価格が上がると大騒ぎするのに、実は米(と流通)についてあまりにも知らなさすぎだと感じました。
1等米等の区分があることまでは知っていても、その違いは「見た目の差のみ」なんてことまでは知らなかったし・・・ひょっとして常識なのかな?
でもまあ、政府に経済安全保障大臣とかがいる時代です。経済はともかく食料安全保障ー具体的には自分の主食である米ーについては、個人レベルでも知っておいたほうがいいな~と反省した次第。
というのはですね、食料安全保障の司令塔たる某役所がまともに機能していないからです。だから国民それぞれが勉強して自衛しないと危ないと思うんですよ。奴らが正しいことを言ってるか信じられないので。
コメ政策は、またしても百八十度転換だ。鈴木憲和農相は24日、自民党の部会で2026年産の主食用米の生産目安について前年比2%減の711万トンにするとし、減産の方針を示した。・・・政権が代わったことで、コメ政策は再び大転換である。石破前首相はコメ不足が米価高騰の要因とし、生産量を抑えて米価を維持する「減反政策」の見直しを掲げ、今年8月には増産への方針転換を打ち出していた。
しかし、新たに農相に就いた鈴木は22日の会見で「需要に応じた生産が何よりも原則であり、基本である」とし、増産方針の転換をにおわせたばかり。
政権や大臣が変わったからと言って、増産するか、減産するか 180度方向転換する時点で官僚機構として異常でしょう(基本日本の省庁というのは、名前を見ればわかるように供給側しか見てないから、新政権の方向が省庁としては正しい。でも安全保障って究極的には需要側の視点じゃない?)。
でもねえ、問題はそれ以前に・・・君たち政策の基本となる「正確な需要予測」は持ってんだよね? 以前は、それが間違ってました、さらに嘘もついてました。すいません という話だったけど。 前大臣が言及したけど、そろそろ政策の失敗について、誰に責任があるか明確に申し上げてくださいな。
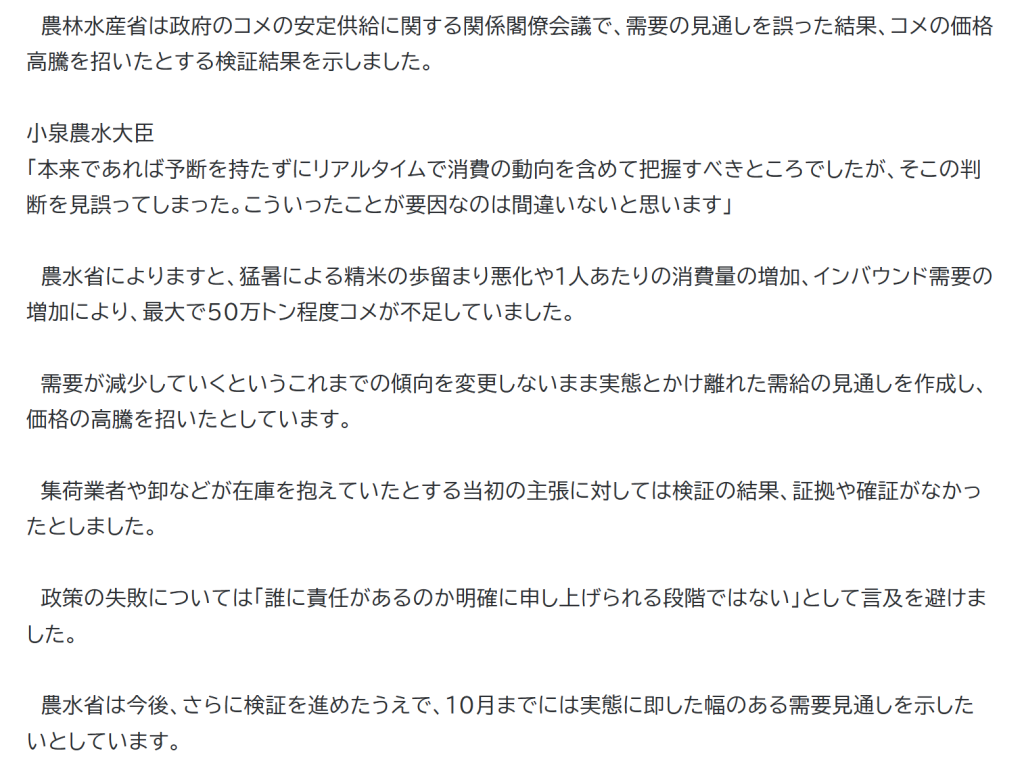
それはともかく、両記事の結論を繋げると「実態に即した幅のある需要見通し」をもとに「需要に応じた生産を行う」ことになりますな。ま、これで物事がまともに動くなんて、僕には思えないけれど。
と、追加した記事には、こんなショッキングな言葉も。 でも、根本的には、この認識が正しそうな気がするなあ。 これは良記事なので、ぜひ原本を読んでほしいな。
もはや日本の気候はコメづくりに適していない
それは、日本の気候そのものが米作りに適さなくなりつつあるという、より大きく、深刻な現実だ。この状況を打破する方法として、生産現場からは高温に強い品種の開発が強く求められている。竹ヶ原さんは次のように指摘する。
「現在、全国で多く作付けされている『コシヒカリ』などの主要な品種は、何十年も前の猛暑が起こる前の環境を前提に開発されたものです。気候がこれだけ変わってしまったので、米の品種もアップデートされなければ対応できないのは当然のことです。国や研究機関が高温に強い品種開発を早急に進めることが必要でしょう」
「令和のコメ騒動」の教訓を活かし、生産現場の声に耳を傾け、データに基づいた的確な政策を打つ。そして、信頼できる羅針盤(統計)を手に、気候変動という荒波に立ち向かうための新たな船(高温耐性品種の開発・技術革新)を官民一体で開発していくこと。それこそが、日本の主食であるコメを未来へつなぐ、真の展望と言えるだろう。JAでも卸売業者のせいでもない「コメ価格高騰」の真犯人が判明…現役農家が明かした「コメが消えた本当の理由」
生産現場が直面する「気候変動」と「農業統計」二つの大問題

元河川技術者、現在は里山保全の仕事をしているおっさんです。西尾市在住の本好き歴史オタク。